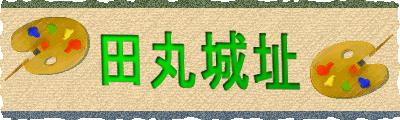
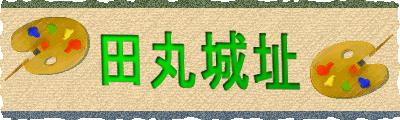
田丸城址
田丸城はもと玉丸城と呼ばれておりました。
玉丸城は南北朝動乱期の延元元年(西1336年)後醍醐天皇を
吉野に迎えようと伊勢に下った北畠親房親子は、神宮神官の度会氏、
一之瀬城の愛洲氏、熊野水軍などの援助を得て玉丸山に砦を築いて
南朝方の拠点とした事が始まりとされております。
大手門跡
これが天守跡です。
北畠氏の養子になった信雄は此処に八間四方高さ九間三層五階建ての
天守閣を建築しました。
屋根は瓦葺ではなく檜の皮で葺いた桧皮葺だったようです。
築城5年後の天正8年(西1580年)に突然天守閣は炎上焼失し信雄は
松阪の松ヶ崎城に移って行きました。
二の丸跡
南朝方の本拠地である吉野から伊勢神宮の外港大湊に通ずる道は
軍事経済の面からも吉野朝廷にとっては重要な路線であり玉丸城は
伊勢神宮をめぐる南朝、北朝の攻防の舞台となりました。
玉丸城をめぐる攻防戦は北朝方との間で幾たびとなく行はれましたが
興国3年(西1342年)築城以来6年目に北朝方に落城しました。
田丸城の落城により北畠顕能は一志郡美杉村多気の霧山城にこもって
初代伊勢国司として伊勢志摩を支配しました。
その間にも戦いは幾たびと無く行はれましたが、元中9年(西1392年)に
南北朝が一つにまとまりまして再び北畠氏が玉丸城を支配しました。
このようにして北畠氏は8代にわたり200年余りの間玉丸城を支配しました。
室町時代の終り頃織田信長の伊勢攻略が始まりました。
信長軍は大軍を以って北伊勢に侵入し、大河内城を攻めましたが
城の守りは堅く城はなかなか落ちませんでした。
その為、信長は次男信雄を伊勢国司北畠氏の養子として和睦をしました。
信雄は伊勢国司の権勢を駆使して田辺の丘を掘り割ってお城の内堀と
しました。
二の門跡
又、外城田川を掘り割って流れを変え田丸の町を囲む外堀としました。
お城には石垣や土塁を積み上げ、天守閣を建築し鉄砲戦に備えた城を築いて天正3年(西1575年)お城に入城しました。
この頃から田丸城と呼ばれるようになりました。
この門は富士見門です。
田丸城内には八ヶ所の門がありました。
三の丸には富士見門と冠門がありました。
冠門は三の丸御書院へ、富士見門は三の丸から二の丸の富士見台に
向かう門でした。
この御門は江戸時代中期のもので往時の原型を留めた唯一の建造物です。
この石垣の積み方を野面(のずら)積みと云います。
野面積みとは自然の形の石を組み合わせて積んだものです。
田丸城内には築城の時に積まれた苔むした野面積みの石垣が
昔のままの姿で今も残っております。
一年後、信雄は田丸城内ほかで北畠一族のほとんどを討ち取りました。
八代具教も三瀬の館で討たれております。
自分の夫に親兄弟を討たれた雪姫は悲しみの余り城内で自害して
果てたと言われております。 (北の丸跡)
その後田丸城主は、田丸氏、稲葉氏、藤堂氏と代わりましたが
元和5年(西1619年)8月紀州領となり初代紀州藩主となった徳川頼宣の付家老
として紀州に従った久野丹波守宗成が8500石を戴いて田丸城主となりました。
その後、加増され1万石となりました。
このようにして久野家は八代にわたり約250年間明治維新まで田丸城を支配
しました。
朝日新聞を創業した村山龍平翁も田丸に生まれ田丸藩に仕えた士族でした。
明治2年に田丸城は廃城となり、同4年城内の建物はすべて取り払われ一部は
民間に払い下げられました。
昭和3年村山龍平翁が当時国有地となっていた田丸城址約10町歩を当時の
金で3万円もの巨費を以って払い下げを受け田丸町に寄付をされました。
この歌碑には村山龍平翁が詠まれました
(いく千とせ、かわらぬことを祈るなり、この城山はこの里の神)
と刻まれております。
その後残りの城地も町有化され現在は皆様方に開放されております。
この二の丸には富士見台があります。
当時はここから富士山が眺められたようです。
天守跡から眺めますと眼下には昭和45年頃に圃場整備されました
30アール区画の水田が並び、玉城町が一望できる綺麗な景色が
広がります。
秋から冬にかけての天気の良い朝方の太陽が昇る直前に
田丸城址の天守跡から富士山が眺められます。
(写真 板谷氏提供)