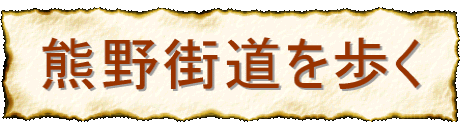
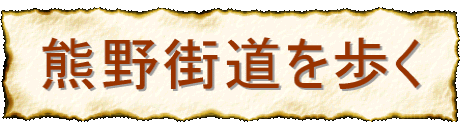
田丸の街を伊勢本街道が通っておりますので、お伊勢参りがが盛んだった江戸
時代中頃にはお伊勢参りを済ませた旅人たちが田丸の宿で一泊をし身支度を
整えて熊野詣に旅立って行きました。
田丸は熊野街道の基点となっております。
街道の近くに松光山大得寺があります。
大得寺は初代田丸城主久野丹波守宗成から八代純固までの菩提寺となっております。
勝田町は終戦後まで芸子屋、料理屋などがあり華やかな街でした。
今も当時の街並みの面影が残っている街です。
右手奥に朝日新聞を創立されました村山龍平翁の屋敷跡があります。
今は香雪園と名付けられ人々の憩いの場となっております。
大橋を渡った街道筋に地蔵堂があり、地蔵さんには(幼夢童子)俗名とよ、嘉永7年
寅5月と刻まれ、もう一つの地蔵さんには万治3年〔秀法童子)とあります。
二つの地蔵さんには、この町の誰かが街道を通る西国巡礼や参宮道者に供養を乞うて
建てられた街道供養地蔵です。
道の向かい側に神照山廣泰寺の道標が建っております。
お寺は宮古にあります。
このお寺は玄虎和尚に依って、文明18年(西1486年)に開かれた曹洞宗の中本山で
ご本尊は木像坐像の釈迦如来です。
お伊勢参りと西国巡礼、熊野詣のおもてなしの一つとして,野篠の入り口に建てられた
接待地蔵があります。
田宮寺の11面観音が国宝に指定された時、安全に旅人を霊場に導く為に、接待地蔵と
名付けられたようです。
当時参宮人と西国巡礼の旅人が行き交わったこの熊野街道は戦中戦後の開発で松原の
面影が今にも消えようとしております。
江戸時代初期から沢山の伊勢詣で客の賑わいで蚊野本郷の人達が移って来て開いた
茶店が軒を連ねて蚊野茶屋の街並みが出来たと言われております。
原の入り口に祀られている円通山、石仏庵は、文明8年3月草創されたと伝えられる
尼寺でありました。
昭和23年廃寺となり、本尊道引観音や秘仏延命子安地蔵は地元光徳寺に預けられて
おります。
境内の道引観音碑には文化2年(西1805年)5月と刻まれております。
熊野街道を挟んだ向かい側には、33体の石像を安置する観音堂があります。
この石仏は西国33箇所の観音石像で文化5年(西1808年)に地元外の人々から
寄進されたものです。
原は広々とした平地をさす地形名で,国束山の北麗の集落が北へ広がり参宮道者や
西国巡礼が行き交うようになって、街道に茶屋が並んで出来た町と言われております。
往時の街並みの面影が残っている町で街道を通る旅人の姿が眼に浮かぶようです。
野中に(左西国道、右吉野高野道)と刻まれた道標が建っております。
右に行きますと吉野街道、左に行きますと熊野街道で、ここは追分となっております。
この道を左にとりますと熊野街道の最初の難所言われております女鬼峠へと向かいます。
昔の旅人はこの道を熊野へ、熊野へと向かって旅を続けました。
熊野街道を行く